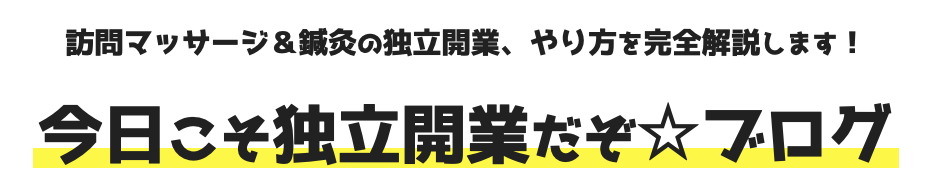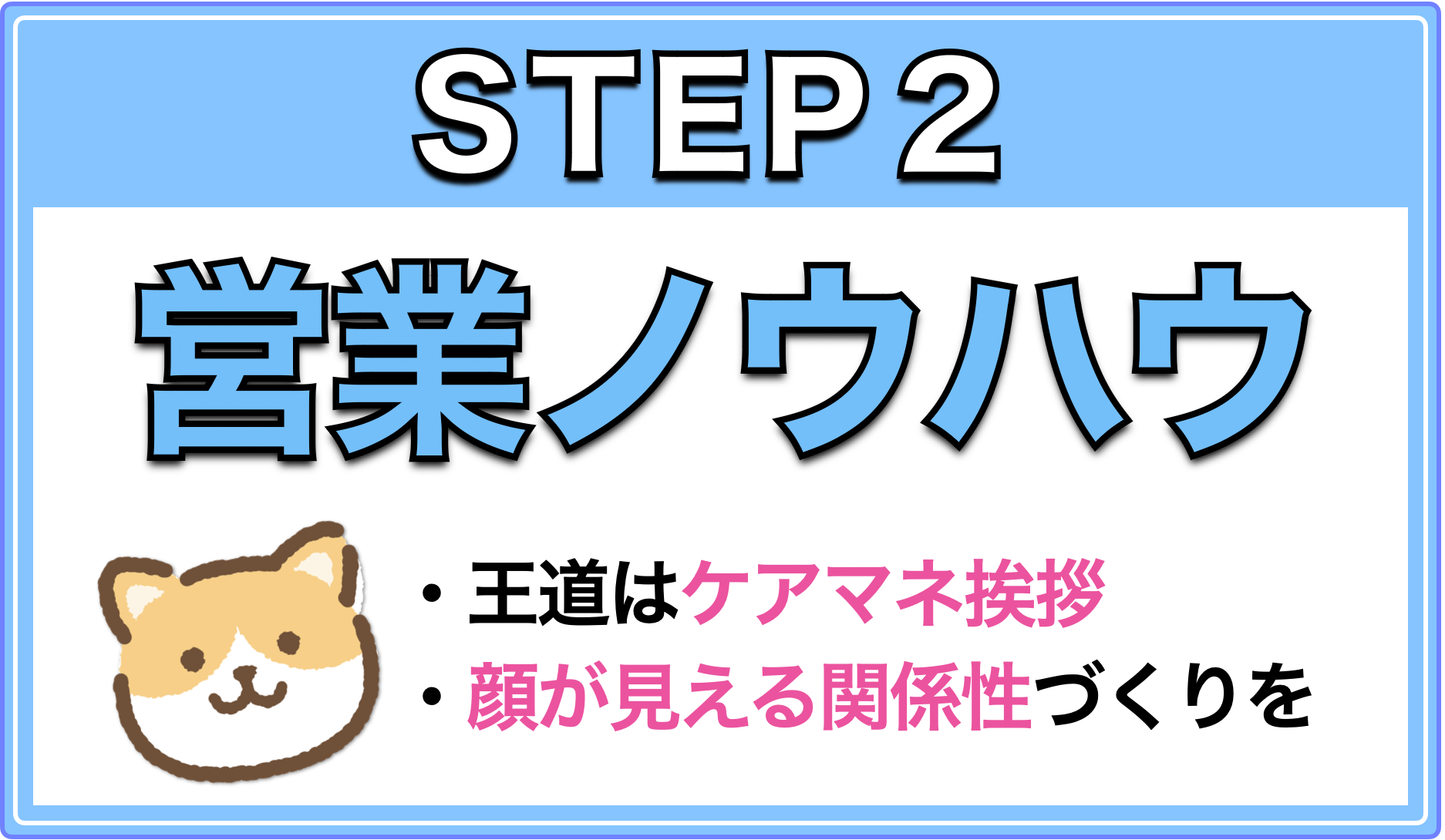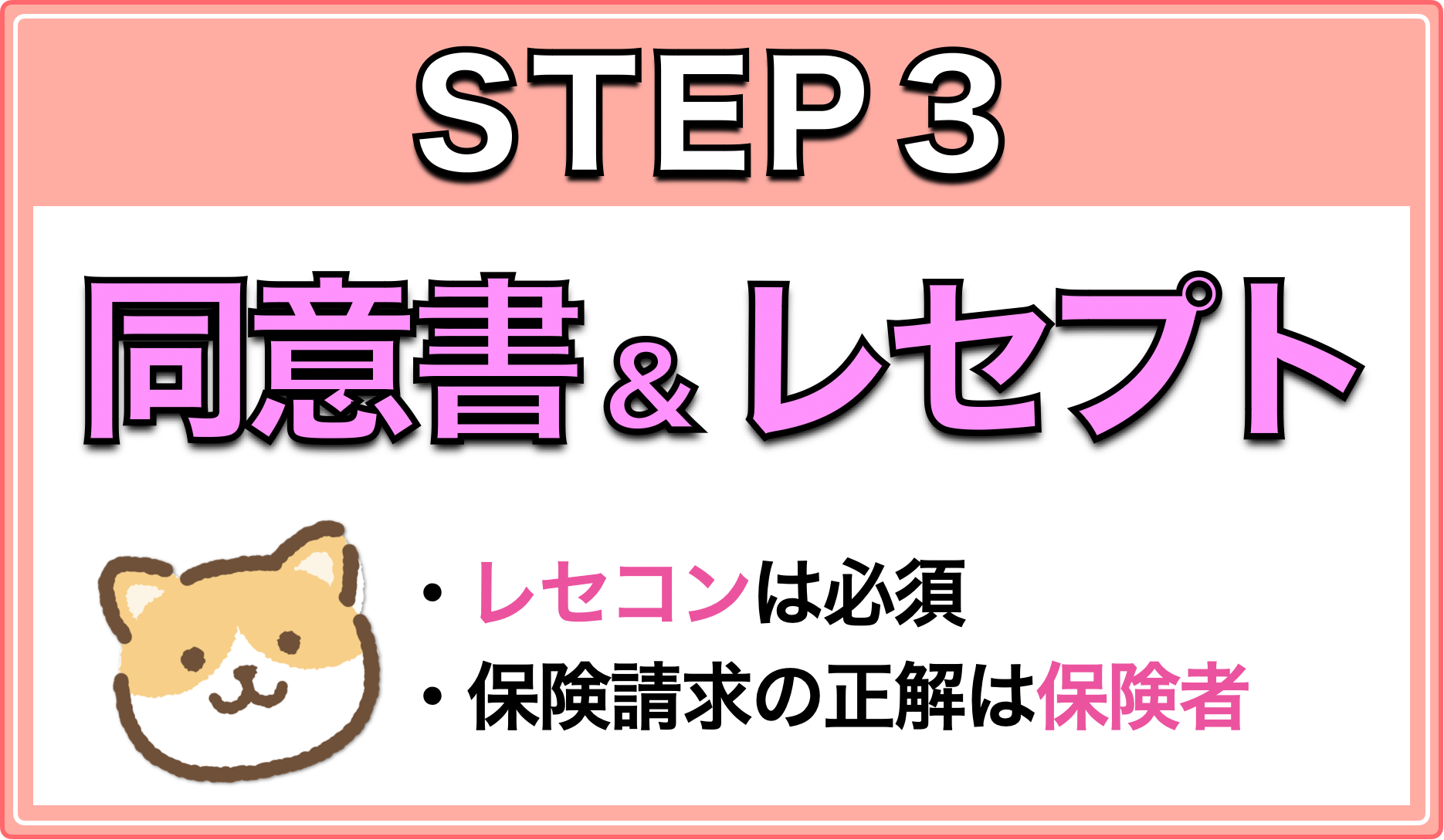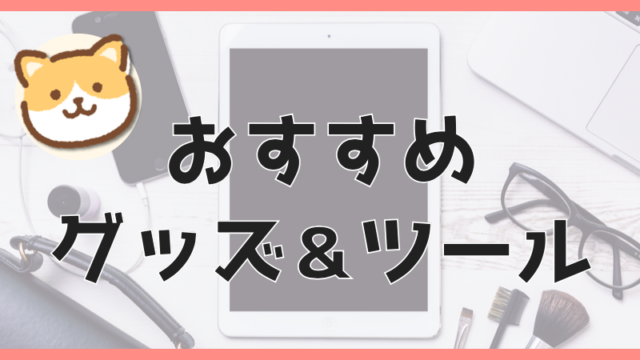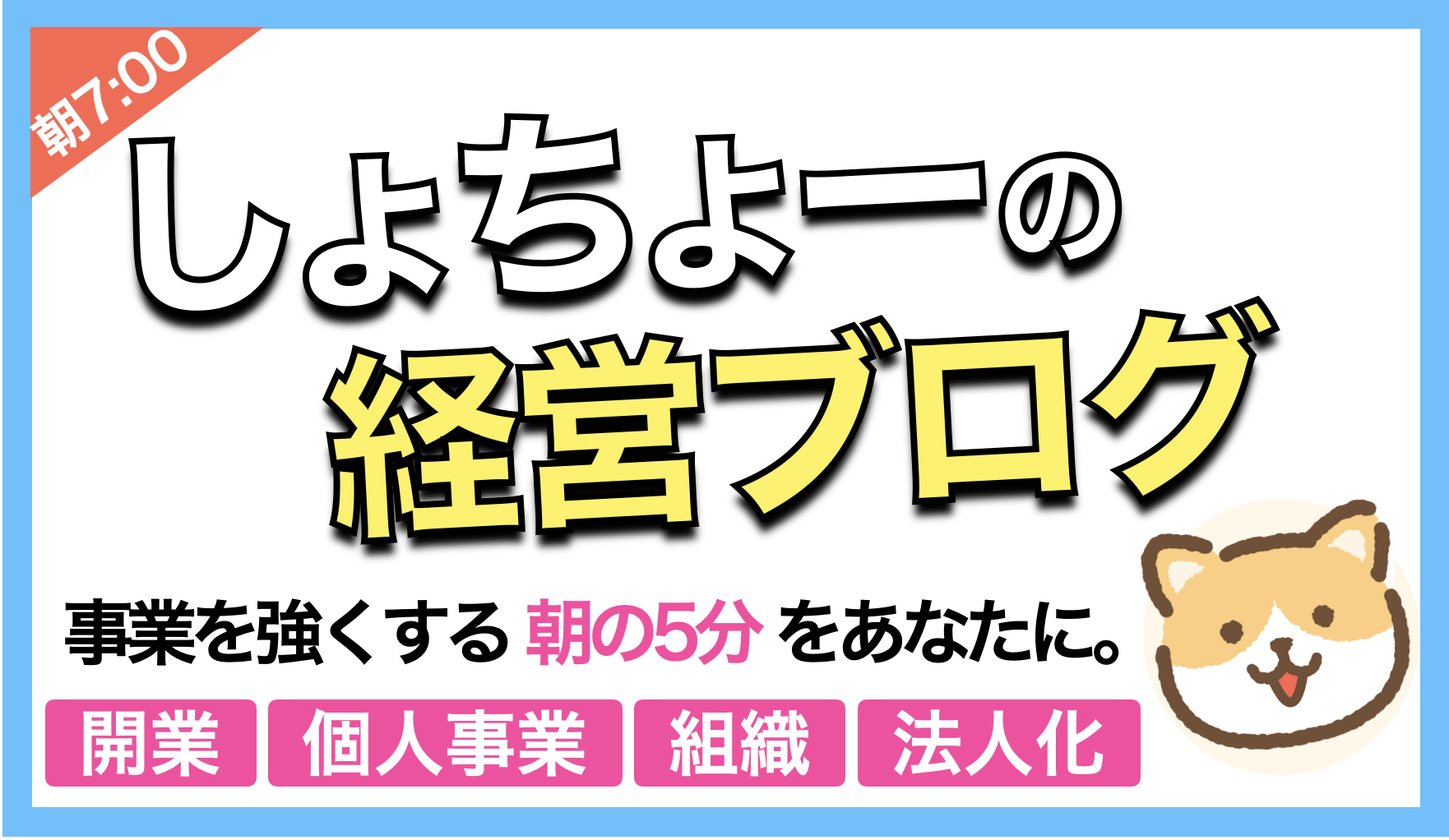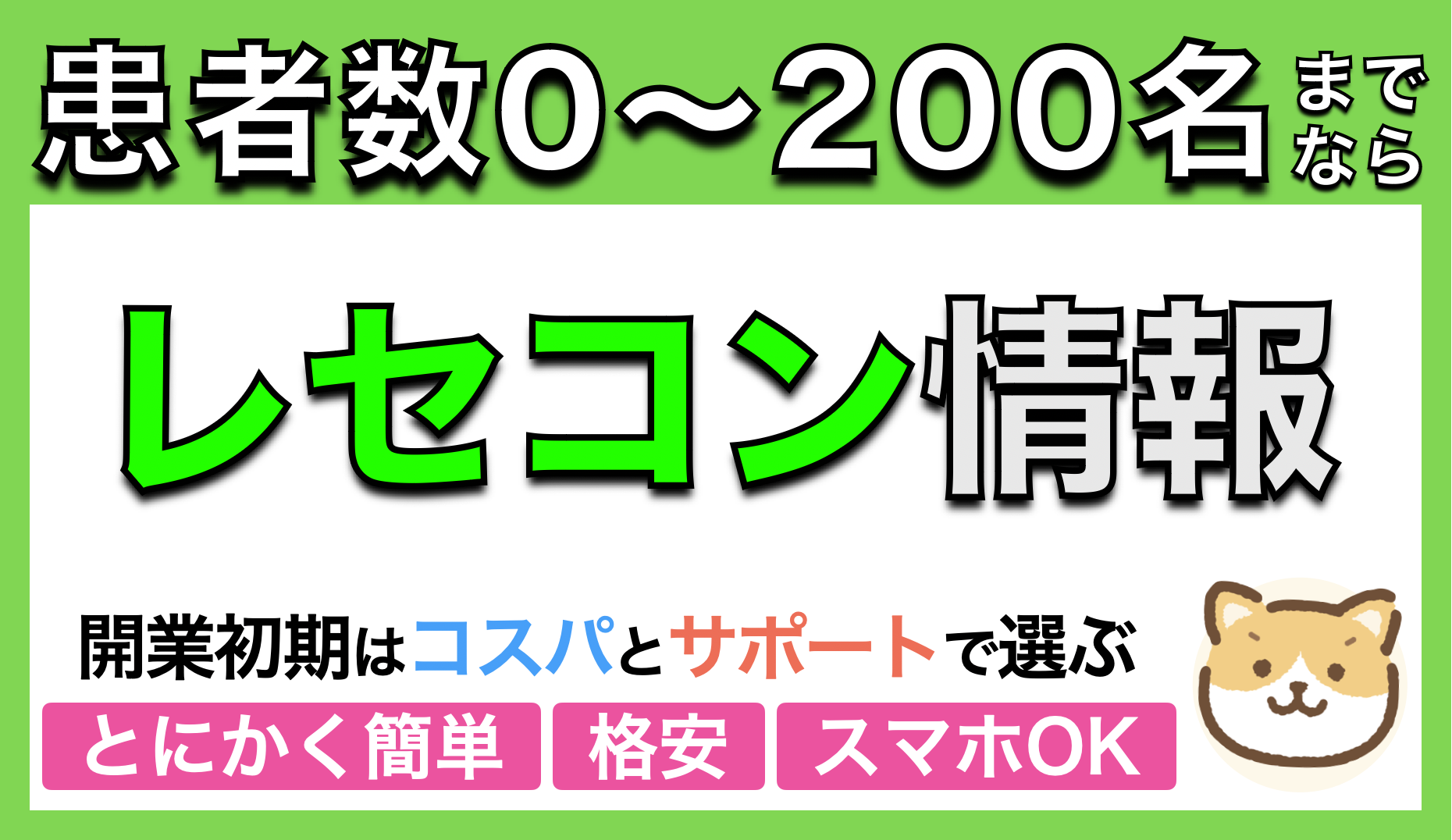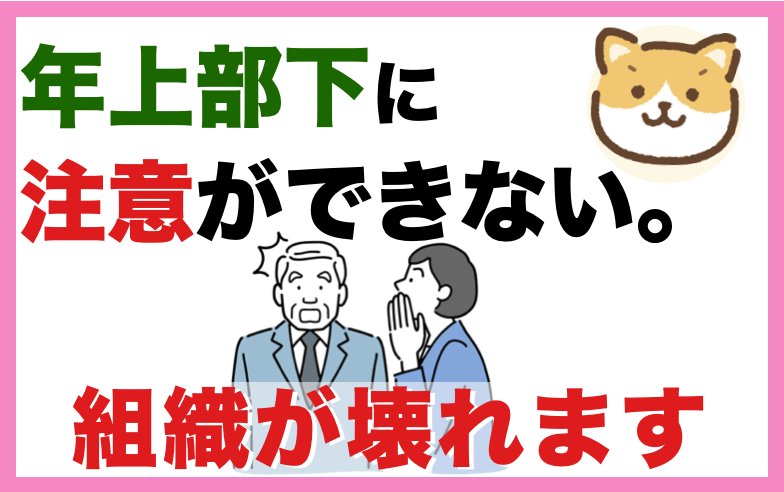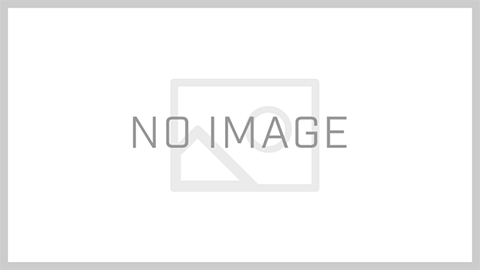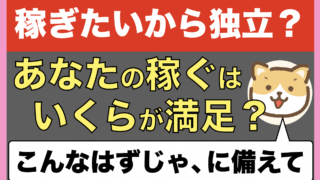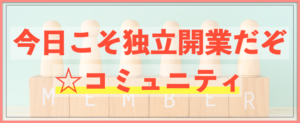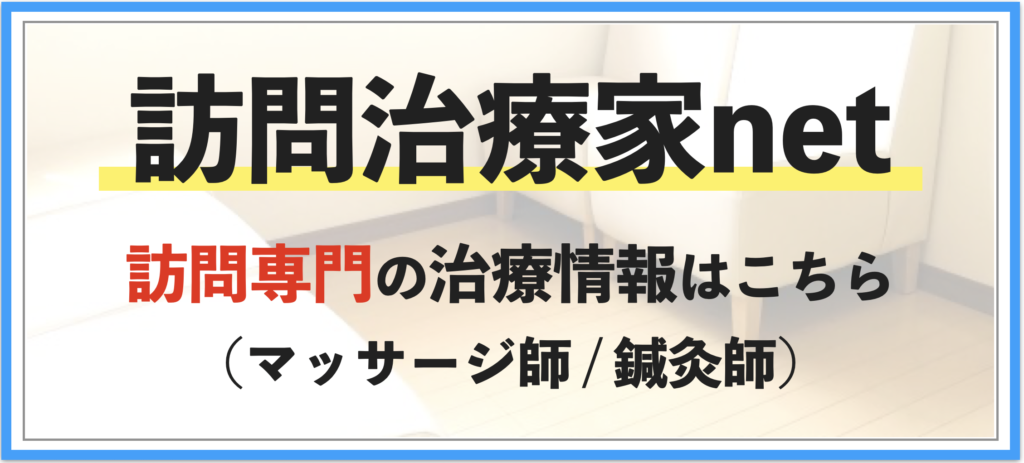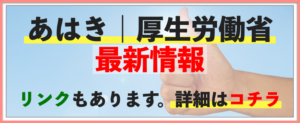こんにちは、しょちょーです。
今日は「年上の部下に注意ができない状況」について、組織運営の視点からお話ししたいと思います。
年上の部下ができるとき
このページを見てくださっている方の多くは、「いつかは独立したい」「今は施術者だけど、いずれ管理職や経営も視野に入れている」そんな方々だと思います。
訪問業界では、年齢層が高いスタッフが多いため、自分より年上の人とチームを組む、もしくは部下として指導する場面が必ず出てきます。
2〜3歳上くらいならまだしも、10歳、20歳、場合によっては40歳上というケースも珍しくありません。
これは本当に難しいんです。
立場上は上司であっても、「年下」というだけで感情が追いつかない。
相手も、「言っても若い子だしな」と見てくる。
どちらも無意識に壁を作ってしまうんですね。
自身の失敗から学んだこと
僕も20代前半から管理職を任されてきました。
当時は経験も浅く、伝え方もうまくない。でも、改善点が見える以上は伝えないわけにはいかない。
そうやって注意した結果、鼻で笑われたり、反発されたり、何度もありました。
「しょちょーが間違ってる」と言われて全く話を聞いてもらえない。
「あんな間抜けとは二度と話したくない」と陰で言われたこともありました(笑)
本当にたくさん悩みました。じゃあ年齢を重ねたらうまくできるようになるのか?
そんなことはありませんでした。年齢を重ねても“自然にうまくなる”ことはない。
注意や指導は、練習して磨いていくスキルなんです。
車の運転やスポーツと同じで、繰り返して身につくもの。
「注意できない」は組織崩壊の始まり
特に訪問業界では、50代・60代の方と一緒に働く機会が増えます。
もちろん、全員がそうではありませんが、転職市場にいる方の中には過去にうまくいかなかった経験を持つ方も多くいます。(企業に所属し活躍している方は普通は転職しません。独立開業においても同様です。何らかの不具合を経験/抱えてしまって転職に望むのです。)
そういう方をチームに迎えるときは、「理不尽を覚悟する」ことも必要です。
ただ、それでも問題があった瞬間、そのときに注意をしないままにすると、確実に組織が壊れます。
なぜなら、管理職というのは「より広く未来を見られる人」だから。
会社全体を見ている立場が、問題を放置すれば、チームの規律は崩れ、組織の信頼は一気に失われていきます。
注意できる環境を“先に”作る
まず必要なのは、「注意し合うことが当たり前」という文化をつくることです。
たとえば、
・●●の場面では注意をします
・▢▢という行動はフィードバックしません
・上司、同僚、部下関係なく、注意をしあえる関係性になりましょう
・注意する側は、フィードバックに徹しましょう
・注意された側は、言う方の辛さも心得ましょう
・双方建設的な時間としましょう
このようにルールを明文化しておきます。
これがあると、社員も「ここは注意される内容だ」と心の準備ができるんです。
しょちょーの会社では「三方良し(自分・お客様・地域)」を基本にしています。
三方のうちどれかが欠けてしまう行動は注意対象です。また、「即レス(すぐ対応)」なども行動指針に入れており、それができていなければ当然フィードバックします。
もしどのような言動が注意対象か分からない場合には、その会社の企業理念を軸にしてください。
企業理念に沿っていればOK。企業理念から逸脱している行為ならばフィードバックを行う。
「仕事をしに来ている」前提を忘れない
会社は“仕事をしに来ている人の集まり”です。
だから、仕事の話をし合うことは当たり前。
サッカーの部活でサッカーの話をするのは当たり前ですよね。
でも、オーケストラ鑑賞中にサッカーの話するのは場違いですよね。
なので、仕事をしに来ている人の集まりの場においては、仕事の話をするのは当たり前なんです。会社は会社の企業理念を実現できるように人が集まり、仕事を通して理念の実現を実践し、報酬をいただきます。
だけど、現実には、「雇われているから」「業務委託だから」といった意識のまま、自分ごととして仕事を捉えられない人もいるんです。
「なんのために会社に来ているの?」
と聞いたときに、本当の意味でちゃんと答えられる人は少ないと思います。
だからこそ、まずは理念や価値観を共有しておくこと。
「仕事の話をする=悪いことではない」と認識してもらうこと。
仕事を通して企業理念の実現を目指すことが集まっている理由なんだよ、と認識してもらうこと。
それが“注意が通じる土台”になります。
注意ではなく「フィードバック」に徹する
注意・叱る・怒る。どれも似ているようで違います。
特に年上の部下に対しては、「叱る」は構造的に成立しません。
注意・叱る・怒る、どれも「年上の人が、年下の人に」行う行為が一般的だからです。なので、年下からの指導は基本的に難しいのです。
ではどうするか?
代わりに、事実をもとにしたフィードバックに徹することです。
たとえば、
上司「この書類、昨日が提出期限でしたが、まだ確認できていませんが、進捗はどうですか?」
部下「すいません、まだ途中です。でも、訪問でずっと色々と忙しいので昨日までの期限じゃ無理ですよ」
上司「そうなんですね、忙しい中でいつもありがとうございます。だけど、事実として期限超過してしまって、事務の方の処理負荷が増えて困ってしまいます。次回からは受けた時点とか、忙しくて期限に間に合わないかも。と思った瞬間に相談をしてもらえませんか?フォローもなにもできなくなってしまいます」
部下「ええ、まあ。善処します」
上司「それと、この書類についてはどうされますか?一緒に考えましょうか。」
結構マイルドな表現に抑えましたが、実際には何故かこちらが罵倒されたりしたこともあります。めっちゃ理不尽(笑)
①まず相手の状況を受け止める
②その上で、事実を共有し、改善策を一緒に考える
この順序が大切です。
「受け止めてから提案する」ことで、相手も守りの姿勢から“協働”の姿勢へと変わります。
基本的に注意される側は「攻撃されている」と感じてしまいます。これは人間なので上司においても同じです。注意される側は身構えるのです。
なので、フィードバックをする上司は「にこやかに、ゆっくりと、安心・安全な雰囲気で」接していくことをおすすめします。それだけでも防御姿勢を崩すことができます。
防御されている間は、こちらの真意は絶対に伝わらないと強く心得て下さい。
あなたのやりたいことは組織の良化ですか?それとも責めて自分の気持ちをすっきりさせることですか?
前者であれば、フィードバックに徹しましょう。
組織は「フィードバックの質」で決まる
注意を後回しにすると、徐々に空気が乱れ、1週間、1ヶ月、半年……気づけば組織全体の空気が変わってしまいます。
逆に、事実ベースのフィードバックをその場で行えば、信頼関係を崩さずに、チーム全体が成長していきます。
嫌われるのが仕事ではありません。
「良くするために伝える」ことが仕事なんです。
まとめ:注意は愛、放置は裏切り
注意をしないことは、優しさではありません。
それは、相手やチームを“放置する”こと。
会社は価値を提供するために集まった仲間の場所。だからこそ、仕事に関しては、年齢も立場も関係なく、フィードバックをし合う文化を築いていきましょう。
そして、
「年上部下に注意ができない」は、組織崩壊の予兆。
放置せず、事実に向き合い、建設的に伝えていきましょう。
今日も一歩ずつ、前へ進みましょう!
皆さんの挑戦と活躍を心から願っています^_^